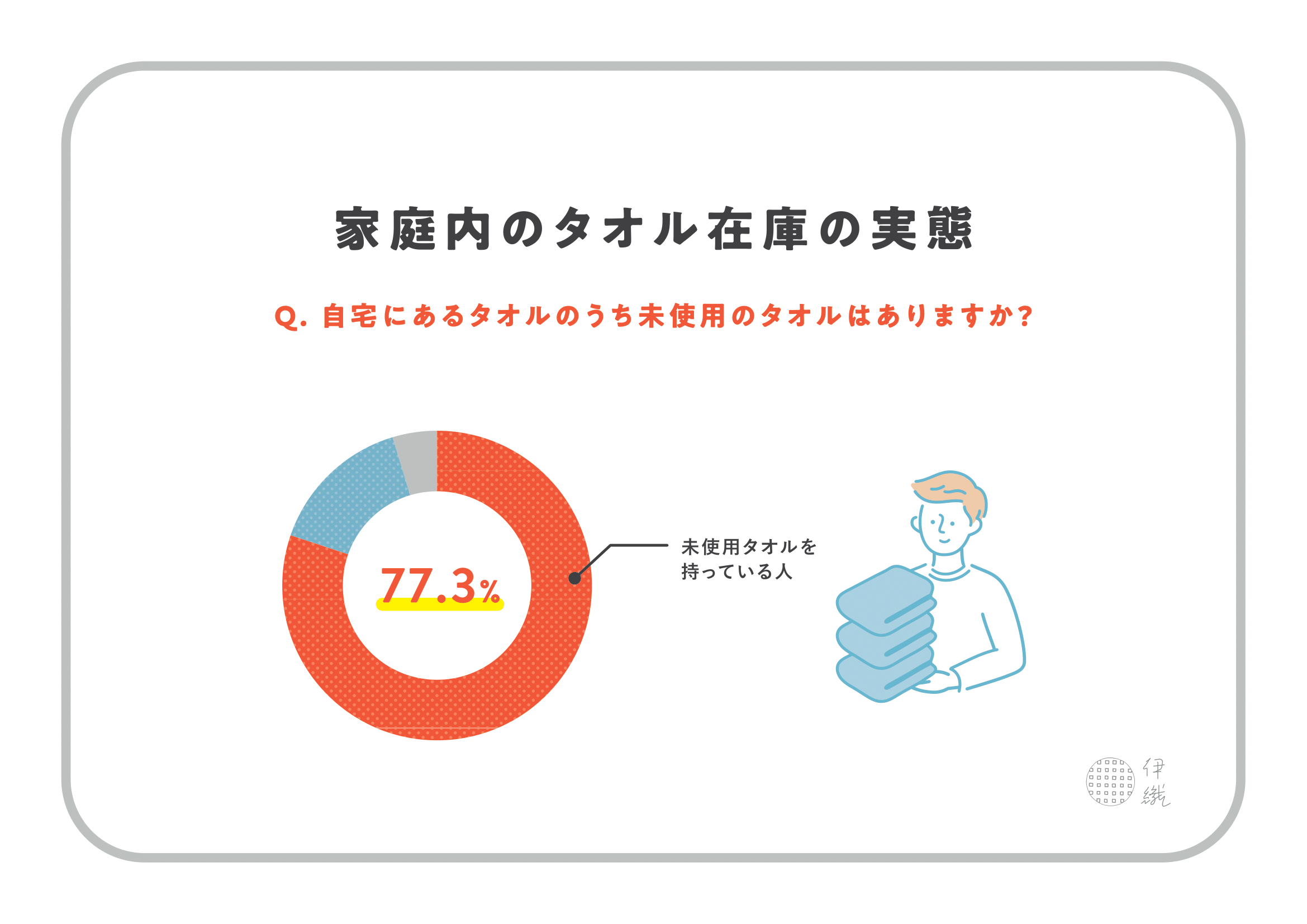【座談会】伊織×伊予かすりの取り組み
「tonari to iyokasuri」ができるまで
インタビュー・テキスト:清水淳子(ジャンボ編集室)
撮影:武智俊介(Maison photostudio)※商品写真、デニム工場部分
1. 「tonari」プロジェクトとは
「隣にも目を向ける」を合言葉に、様々な事業者とアップサイクルや協業を考える、「伊織」のサステナブルプロジェクト「tonari」シリーズ。
2009年に立ち上がった「伊織」は、多くのタオルを皆さまにお届けしてきましたが、生産量や店舗数が増えた一方、規格外品(B品)や製造過程で発生する残糸など、“つくり手としての責任”を感じる場面も増えていきました。そんな中、これまで今治タオルの残糸をアップサイクルしたタオルシリーズの他、奈良の老舗靴下メーカーとコラボして作ったタオルの残糸の靴下など、様々なアップサイクル製品を生み出してきました。

今回は日本三大絣のひとつであり、愛媛県の伝統的特産品で無形文化財にも指定された「伊予かすり」とコラボし、2種類のかばん、トート「TOOL」とショルダー「NOTE」がようやく完成しました。
繊維産業として長い歴史のある、かすりとのコラボのきっかけと約2年にわたる商品開発の話をお伺いするべく、白方興業株式会社・代表取締役、白方基進さんと部長の柴田幸雄さん、そして株式会社伊織・代表取締役、村上雄二による座談会を行いました。
2. 伊織と伊予かすりの出会い
―「伊予かすり」の白方興業とタオル専門店である「伊織」との出会いについて教えてください。

村上:愛媛の伝統的特産品「伊予かすり」を後世に残す活動を続けているということに尊敬の気持ちがあり、2018年に「民芸伊予かすり会館」とのコラボレーションでタオルハンカチシリーズ「IYO KASURI」を作らせていただいたことがきっかけです。
白方:お互いの良さを生かした商品ができないか、ということで、「伊予かすり」の伝統柄をモチーフにしたタオルハンカチを作らせてもらいました。一緒に記者会見をしたことも覚えています。

※上から「昔日(せきじつ)」、「玉串(たまぐし)」、「慈雨(じう)」
柴田:昔日と玉串は古くからある伝統的な織り柄で、慈雨は「21世紀えひめの伝統工芸奨励賞」を受賞した織り子さんオリジナルの柄です。ハーフサイズのタオルハンカチで私自身も愛用しています。
―お互いの企業の魅力、会社の取り組みについてどう感じていますか。
村上:長年地域に根付いている伝統産業を守ろうとしているところに、とても共感します。「伊織」はタオルをメインにした事業を展開していますが、今、タオル産業があるのも、かすりがあったからこそ。そういう意味でもリスペクトしています。何かご一緒できれば光栄だなと、当初から思っていました。

白方:着物が日常着ではなくなり、かすりの需要が減っていく中で伝統産業を守り、その作り手をどうにかつないできましたが、新たな商品開発や企画力などは「伊織」さんが優れているところだと思います。かすりが今の生活にフィットする商品に生まれ変わり、活用ができるような取り組みができればいいなと思っています。
―お互いへのリスペクトがありつつ、協業を進めてきたのですね。
村上:タオルハンカチのコラボがあり、その後も「何か一緒にやりたいですね」という話をしていた時に新型コロナウイルスの広がりがあり、積極的な取り組みがしづらくなりました。
コロナ禍で大きな動きができなくなった代わりに、自分たちの足元を見つめ直す期間ができたことで「tonari」プロジェクトが生まれ、自分たちが住む地域のことや豊かな暮らしとは、という問いを企業としても模索することになりました。そしてコロナ禍が落ち着いたタイミングで柴田さんから、「何かまたやりませんか」とお声かけいただき、再びつながることができました。
3. 素材の良さを生かした魅力的な商品作り
―どのような過程を経て商品開発されたのでしょうか。

柴田:最初はオーナー同士で再び協業しよう、というすり合わせをしましたが、どのような商品になるかは見えていませんでした。私としては、タオルハンカチの第二弾のような、かすり柄の商品かな、と想像していましたが、話を進める中で「かすり自体をぜひ使いたい」というオーダーがあり、企画が一からスタートしました。
村上:様々な商品を検討しましたが、せっかくなら日常で使えるものがいいだろう。そして、部屋の中で使うものよりも、外にも持ち出せるものがいいのではという意見が社内でありました。
カバンであれば、毎日使うことで愛着も湧くし、いろんな人に見てもらえるので、取り組みを知ってもらうきっかけにもなります。素材の良さをちゃんと生かして、今のライフスタイルに自然に入り込むような商品というのが必要だと思い、そういう意味では、このトートバッグとショルダーバッグはぴったりかなと思っています。
柴田:かすりに関して言えば、どこにどう使うかがポイントです、というお話をさせていただきました。
「伊予かすり」は、現在は手織りのみの生産で、大変貴重なものになっています。私たちの手元にある反物のストックの中から選んでいただくことになりますが、着物のために作っていたかすりは大柄なので、バッグに活用するのであれば小柄なものが向いているのではないかと。

村上:かすりって、どうしても上の世代の方が使うイメージがあると思いますが、そこも前向きに変えたいなという想いがありました。貴重なかすりをたくさん使うと価格が上がってしまいますし、効果的にポイント使いをして、年齢問わず若い人たちにもいいなと思ってもらえるような商品にしたいと思いました。
白方:内側にはタオルを、外側はデニムを使っているんですね。
村上:「tonari」プロジェクトで作り続けてきた残糸のタオルを内張りに使い、クッション性や吸水性など、カバンを作る際に「あったらいいな」と思う機能を備えることができました。耐久性や機能性を考えてシャーリング加工(ループ状に織られたパイル生地の表面を平らに切りそろえる)をして、スベスベした手触りのタオルに仕上げました。

外側は福山デニムを使用しています。内張りのタオルを作ってくれている協力工場さんの紹介で、広島県の「篠原テキスタイル」さんと出会うことになりました。100 年以上の歴史をもち、海外ハイブランドの生地も手がけるデニムメーカーですが、工場にお伺いをした際に行き場のないB反生地があるというお話を聞き、今回のプロジェクトでぜひご一緒できればということになりました。


白方:福山デニムは「備後絣」がルーツにあると聞きます。そこで培われた染色技術が、福山市がデニムの産地として発展するようになった背景にあるそうです。ここでも何かご縁のようなものを感じます。うまい具合に、かすりとデニムとタオルという、いとこ同士がくっついたような商品ができましたね。
4. 使い込まれた美、古くて新しい価値観
―商品を開発する上でこだわったところや苦労したところについて教えてください。
村上:まずは使い勝手の良さですね。男性にも女性にも幅広く使っていただきたいので、今のライフスタイルに合わせた機能性にこだわりました。
苦労した点は、伝統的特産品を素材に使っているから、高くて当たり前、一般の方に手が届かない商品にはしたくなかったので、メリハリをつけてなるべくコストを抑えることは、かなり意識しました。検討を重ねて、かすりはハンドル部分とサイドにワンポイントで入れました。

白方:かすりは繊細な織物でもありますから、普通に考えたら最も手に触れる部分に使うのは避けたいんじゃないかと、はじめは驚きました。使っていくうちに擦り切れたり破れたりする可能性が高いですから。
村上:ハンドル部分に利用した理由は、デザイン的な要素と伝統的なかすりを目で見て触って、身近に感じていただく目的もありますが、その昔、野良着としてボロボロになるまで直しながら使われていた、かすり本来の役割を、時間をかけて再現していくことで、使い込まれる美しさや愛着を生むきっかけになるのではという思いを込めています。
白方:その話を聞いて、確かにジーンズだって使い込む良さが評価されていますし、時間をかけて自分だけの「味を出す」という価値観も素敵だなぁと思いました。ステッチで補強を入れた縫い方をしているので、経年変化を楽しめる仕様にもなっていますね。
あと、機能面では収納ポケットが多いのはありがたいと思いました。決まったところに物を置かないと、どこに何があるのか忘れてしまう男性は割と多い気がします(笑)。スマホはここ、パソコンはここに入れると決まっていると整理がしやすくていいですね。

―村上さんのお気に入りのポイントはどこでしょう。
村上:まずはデニム、タオル、かすりの3つの素材の良さを生かしきれたところでしょうか。ディテールについてもポケットのサイズや位置、ステッチの幅や色など、何度もテストをして細かい調整を繰り返してきました。ショルダーバッグも、体型や用途によって持ち手の長さが変えられる方がいい、という声を受けて、調節可能なタイプへと変更しました。

何より今回、協業させていただいて、かすりを商品にどう落とし込むかを考える過程で学びがありました。使い込んでいくカッコよさというのもありますし、今後の展開にもつながるのではないかなと期待しています。
白方:実は最近リサイクルの免許をとりまして、古いかすりを集めて再生・再利用しようという取り組みを始めています。かすり製造はより貴重なものとなり、事業として続ける厳しさはありますが、「伊予かすり」の伝統や文化は次世代に受け継いでいくべきだと考えています。こういった違う素材(企業)が組み合わさることでそれぞれの課題に気づいたり、新たな価値が生まれたり、とても学びになりました。
村上:今回のプロジェクトで使用したかすりの量は小さなものかもしれません。しかし、「伊予かすり」という素材の価値をあらためて伝える意義、そして商品として流通できなかったかもしれない職人仕事を生かせたという意味において、白方興業様、篠原テキスタイル様、そして弊社が手を携えたこの取り組みは大きな一歩だったと私は思います。

*オンラインショップにて5月23日(金)より販売開始となりました。
TOOL(トートバッグ)
https://www.i-ori.jp/c/iori/iori_tonari/tonaritoiyokasuri/gd4571
NOTE(ショルダーバッグ)
https://www.i-ori.jp/c/iori/iori_tonari/tonaritoiyokasuri/gd4572
※店舗では、伊織本店(松山市道後)、松山お城下店(松山市大街道)、KITTE丸の内店に順次入荷予定となります。


 前の記事
前の記事